
公認会計士と税理士の違いが知りたい!
こんな疑問を解消します。
公認会計士と税理士は
どちらも会計系の難関国家資格。
名前は聞いたことはあっても、
他業種で両者の違いを細かく理解している方は少ないです。
本記事では、
- 公認会計士と税理士の仕事内容の違い
- 公認会計士と税理士の試験制度の違い
- 税理士から公認会計士になれるか
- 公認会計士と税理士どっちがおすすめか
を紹介します。
本記事を読めば、
公認会計士と税理士の違いを完全に理解できます。
公認会計士と税理士に興味のある方は必見の内容です。
筆者は公認会計士と税理士の
両資格保持者です。
本記事では実際に仕事をしている立場から
リアリティのある内容を紹介しています。
本記事にはプロモーションが含まれています
公認会計士と税理士の違いは?

公認会計士と税理士の違いを、
- 公認会計士と税理士の
仕事内容の違い - 公認会計士と税理士の
試験制度の違い
に分けて説明していきます。

一つ一つ丁寧に説明してきますね!
公認会計士と税理士の仕事内容の違い

公認会計士と税理士は
専門とする分野が異なり、
- 公認会計士=会計
- 税理士=税務
という違いがあります。

会計と税務…何が違うの?
正直この2つはかなり似ていて、
重なり合っている部分も多いんですが、
最大の違いは目的です。
- 会計:利害関係者に対し正しい経営成績/財政状態を伝えること
- 税務:課税の公平を保つこと
という目的の違いがあります。
会計の利害関係者は主に投資家を指しますが、
税務の対象は全ての国民です。

税理士は日本国民全員に
関わる仕事なんです!
会計士はそれに比べて
対象範囲が狭いです。
仕事内容の違いは、
会計と税務の目的の違いにより生まれるものが多いですね。
順番に説明していきますね。
違い①:独占業務が違う
公認会計士と税理士には、
どちらも資格をもっていなければできないと
法律で定められている仕事(独占業務)があります。
それぞれの独占業務は以下のとおり。
- 会計士:会計監査
- 税理士:税務代理・税務書類作成・
税務相談

分かんない!
特に会計監査!
ですよね。
会計監査とは、
会計監査(かいけいかんさ、英語:financial audit、auditing)とは、企業、公益団体および行政機関等の会計(決算)に関して、一定の独立性を有する組織が監査と最終的な承認を行うことである。なお、会計検査院による国等の行政機関等に対する監査を特に会計検査と呼ぶ[1]。
Sourced by Wikipedia
これも分かりにくいですが、
簡単にいえば
会社が作った会計書類をチェックすることです。
一方、税理士の独占業務(税務書類作成や税務代理)はなんとなく想像つくかと思います。
クライアント(会社・個人)の代わりに
国に提出する税務関係の書類を作ってあげる仕事ですね。

会計士は
「会社が作った書類のチェック」
税理士は
「会社の書類を作ってあげる」
という違いなんです。

そう聞くと全然違うね!
むしろ逆じゃん!
そうなんです。
会計士はチェックする立場なので
会社と対立することもしばしば。
一方、税理士は会社(や個人)の書類を
作ってあげるので、
お客さんに寄り添って仕事をすることができます。

全員がそうではなくて、
会社の代わりに
会計書類を作る会計士もいるし、
会社の税務書類をチェックする
税理士もいるけどね!
違い②:クライアントの違い
公認会計士の独占業務である監査の対象は
上場企業など、いわゆる大きな会社だけ。
一方税理士の独占業務である税務の対象は
会社に限らず個人事業主なども含まれます。

税理士の方が圧倒的に対象が広いんです
なので、
公認会計士のクライアントは大手企業、
税理士のクライアントは中小企業が中心です。

街中で「会計事務所」って
見たことありますかね?
そういうところは税理士業務をして、小さい会社や個人を相手にしてます!
起業したばかりのスタートアップ企業や
ベンチャー企業などの小さい会社であれば、
税務だけでなく会計も税理士が担当します。

公認会計士の出番は
上場が見えてきたあたりから!
違い③:働く先(勤務先)の違い
公認会計士は大企業、
税理士は中小企業や個人を対象に仕事します。
公認会計士は
- 監査法人
- 事業会社
- コンサルティング
- CFO
などなど、
何をするにしても有名な大企業が勤務先になります。

私は監査法人に勤めてますが、
外国で自分の会社を言うと
みんな知ってるくらい有名です!
公認会計士の勤務先は都心部に多いので、
東京・大阪・名古屋・福岡などに
勤める人が多いですね。
一方税理士は、
- 個人の税理士事務所
- 税理士法人
- 国税庁
- 事業会社
などが勤務先。
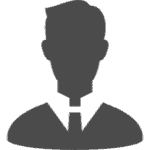
税理士になったら
独立してやりたい!
という人も多いので、
大手税理士法人に最初に勤めても、
その後に独立する人が多い。
税理士は個人でもできるので、
地元の地方などに事務所を開く人も多いですね。

税理士は2世3世が多くて、
実家が税理士事務所という
人も多いですよ!
合わせて読みたい
>>公認会計士の仕事内容は?つまらないって本当?現役会計士が本音で語ります!
違い④:年収の違い
公認会計士と税理士の年収は
比較しにくいですが、
一般的に公認会計士は1,000万円、
税理士は700万円が平均といわれています。

公認会計士の方が高いんだね!
税理士の方が修行期間が長いんですよね。
公認会計士はすぐに監査法人に入って
30代そこそこで1,000万円稼げますが、
税理士で独立して1,000万円を稼ぐまでは
別の事務所で働いたり修業のような期間が必要。
そのあたりが関係して
平均値は税理士の方が低いですが、
実力主義の世界なので稼げる人はどっちでも稼げます。
合わせて読みたい
>>監査法人の年収/職場環境
合わせて読みたい
>>公認会計士になったら年収1,000万円余裕で超えた話【実体験】
公認会計士と税理士の仕事内容の違いまとめ
公認会計士と税理士の
仕事内容の違いは以下のとおり。
| 公認会計士 | 税理士 | |
| 独占業務 | 会計監査 | ・税務代理 ・税務書類作成 ・税務相談 |
| クライアント | 大手企業 | 中小企業/個人 |
| 勤務先 | 大手企業 | 個人事務所が多い |
| 年収 | 最初から高い | 独立してからは実力次第 |
公認会計士と税理士の試験制度の違い

公認会計士と税理士は
どちらも難関国家資格ですが、
受験資格や形式など様々な違いがあります。
順番に説明していきますね。
試験制度の違い①:受験資格の違い
公認会計士の受験資格はありません。
誰でも受験のできる非常に開かれた資格試験です。
一方、税理士の受験資格は、
・大学又は短大の卒業者で、法律学又は経済学を1科目以上履修した者
https://lmoblog.com/what-is-tax-accountant
・大学3年次以上で、法律学又は経済学を1科目以上含む62単位以上を取得した者
・一定の専修学校の専門課程を修了した者で、法律学又は経済学を1科目以上履修した者
・司法試験合格者
・公認会計士試験の短答式試験に合格した者(平成18年度以降の合格者)
・日商簿記検定1級合格者
・全経簿記検定上級合格者(昭和58年度以降の合格者)
・法人又は事業を行う個人の会計に関する事務に2年以上従事した者
・銀行・信託会社・保険会社等において、資金の貸付・運用に関する事務に2年以上従事した者
・税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助事務に2年以上従事した者
などなどたっぷり。
経済・経営系の大学を卒業していれば
たいてはクリアできるようになってますが、
そうでなければ簿記1級を取得するのが一番の近道ですね。

大卒か簿記1級か…
結構大変なんだね。
ちなみに、
公認会計士をとれば税理士はついてきます。
公認会計士の方が難易度が高いですが、
受験資格のために簿記1級を目指すくらいなら公認会計士を目指すのもありかもしれません。
よければ、
簿記1級に関する記事もチェックしてみてください。
試験制度の違い②:受験形式の違い
公認会計士の受験形式は、
- 2次試験方式
- 1次はマークで浅く広く、
2次は論述で狭く深く出題 - 科目数は1次は4科目、
2次は6科目 - 科目合格はなくはないが、
基本的に1度で全科目に受かる
必要がある
ざっとこんな感じ。
公認会計士試験は2次試験方式で、
基本的に一度に全科目合格しないといけません。
これが公認会計士試験の大変なところで、
科目数が多いのに内容が難しいので
勉強時間が膨大にかかります。

資格試験の中では
弁護士と同じくらいの難易度。
日本で1.2位を争う難しさです
一方、税理士の受験形式は、
- 1次試験方式
- 科目数は11科目で、
そのうち5科目に合格する必要あり - 1科目ずつ受験可能
ざっとこんな感じ。
税理士の特徴は1科目ずつ受験可能な点。
確かに1科目ずつは難しいんですが、
一年間集中して勉強することができるため、
科目数が多い公認会計士よりも楽です。
しかも税理士になるために必要な
5科目のうち、2~3科目は簡単な科目を
選ぶこともできるので、資格を取るだけならそこまで難しくないです。

受験形式は一長一短。結局は
合う合わないの話ですね!
試験制度の違い③:受験科目の違い
公認会計士の受験科目は、
- 財務会計論
- 管理会計論
- 監査論
- 企業法(会社法/商法/金融商品取引法)
- 租税法(法人税/所得税/消費税)
- 経営学or経済学or民法or統計学
の6科目。このうち、
- 財務会計論
- 管理会計論
- 監査論
- 企業法
の4科目は、1次・2次共通の科目です。

公認会計士にも
税務の科目があるんだね!
あります。なので、
公認会計士をとると税理士がついてくるんですよね。

でも税理士よりも浅く広いので、
知識の差はかなりあります
税理士の受験科目は、
《会計学に属する科目》
※必修
- 簿記論
- 財務諸表論
《税法に関する科目》
※3科目選択、太字の科目はいずれか1科目を必ず選択
- 所得税法
- 法人税法
- 相続税法
- 消費税または酒税法
- 国税徴収法
- 住民税または事業税
- 固定資産税
一応5科目とれば税理士にはなれますが、
- 法人税
- 所得税
- 消費税
- 相続税
のいわゆる国税4法は
この中でも特に難易度の高い科目になります。

だったら受けなければ
いいんじゃないの?
この4法を知らないと、
税理士として仕事するの難しいんですよね。
だから実質的には受けざるをえないというのが実情だったりします。
試験制度の違い④:難易度の違い(平均勉強時間・合格率)
それぞれの資格の平均勉強時間と
合格率は以下のとおり。
- 平均勉強時間:3,500時間
- 合格率:10%前後
- 平均勉強時間:2,000時間
- 合格率:15%前後
公認会計士の方が若干難しいですね。
合わせて読みたい
>>公認会計士試験の勉強時間3,500hは本当?【結論:半分本当です】
合わせて読みたい
>>公認会計士の合格率10%にビビる必要ない3つの理由
試験制度の違い⑤:合格年齢の違い
それぞれの資格の平均合格年齢は以下のとおり。
- 公認会計士:25歳
- 税理士:およそ26歳
税理士は正式な数値が出ていないので
おおよそですが、
若い人ほど合格率が高いというデータがでています。
ただ税理士の方は科目合格を含んでいるので、
5科目取得の年齢でいうと30歳近くでしょう。
税理士から公認会計士の登録ができるか

公認会計士をとると税理士もついてきますが(登録ができますが)、
税理士をとっても公認会計士はついてきません(登録できません)。
どっちも欲しければ、
公認会計士をとればOKです。

税理士協会からの圧力が
すごいので、
もしかしたらいつか
とれなくなるかも…。
公認会計士と税理士どっちがおすすめか

人にもよりますが、
私の意見は公認会計士ですね。
- 若いうちになれる
- 年収が高い
- 税理士にもなれる
この辺の理由から、
公認会計士の方がおすすめです。
公認会計士は大学在学中の合格も
狙えますが、税理士は受験資格がネックとなり在学中の合格はなかなか難しい。
公認会計士の方が早いうちから年収が高く、
しかも税理士にスライドすることも可能。

親が税理士でも子供は会計士という
パターンは多いです!
税理士やるために会計士
取る人もいますよ!
合わせて読みたい
>>公認会計士とったら社畜になるどころか自由な人生を手にできた話【体験談】
公認会計士か税理士を目指そう!
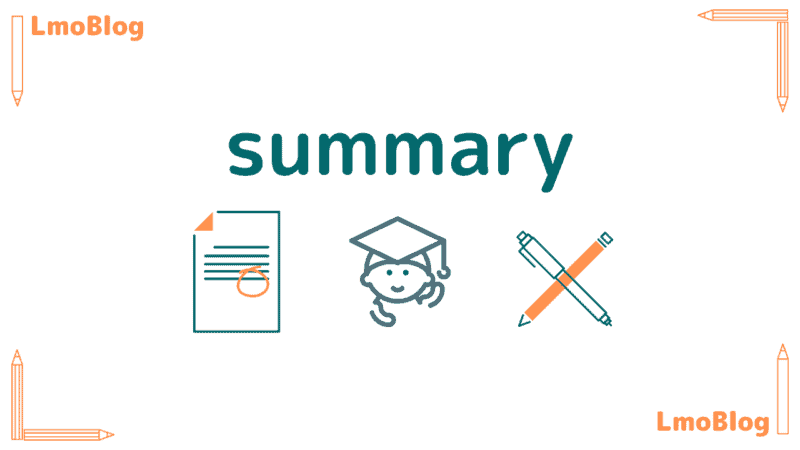
色々と比較してきましたが、
難関国家資格であり、
とれば食うに困らない資格である点は共通です。
他の食える資格は
こちらの記事をどうぞ。
合わせて読みたい
>>食える文系資格はコレ!おすすめ資格10選【2020年版】
それぞれの資格が気になる方は
他の記事もチェックしてみてください。
それでは。



